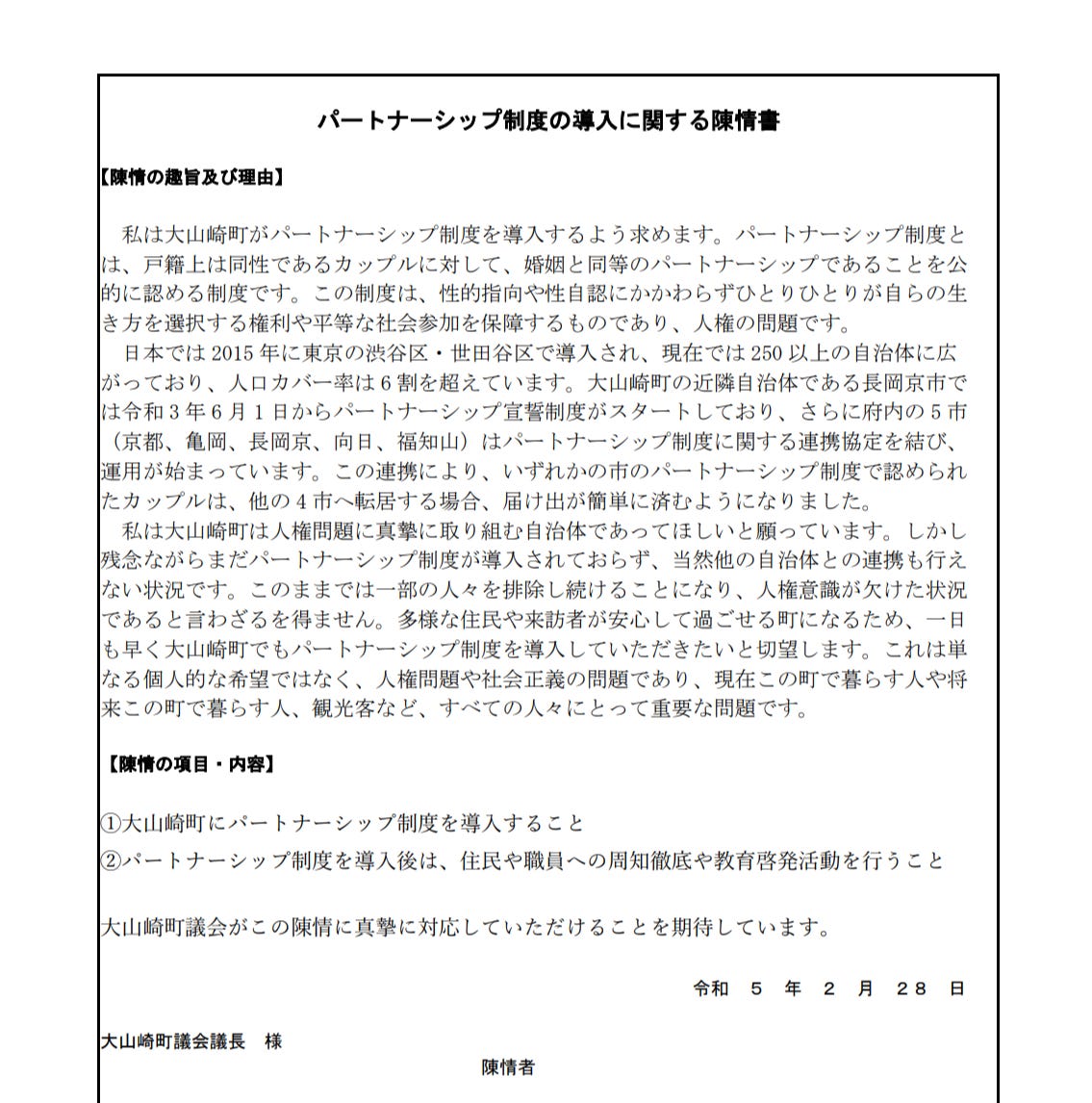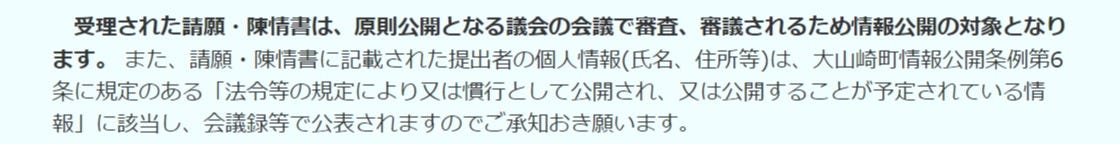パートナーシップ制度の導入を求める陳情が逆転採択されるまでの経緯。とそこで気づいた問題点。
僕のSNSを見てくださっている方はご存じかもしれませんが、先月(2023年3月)は、大山崎町議会(京都)への陳情を巡る一連の活動に多くの時間と労力を注ぎ込んでいました。
今回は、この陳情にまつわる一連の経緯とその中で僕が感じたことなどを書きたいと思います。自分の中で整理しておきたいというのが大きな動機ですが、これらを共有しておくことは、政治に対して何かしら問題意識を持っていたり、投票以外の方法での政治参加を考えている人にとっては、それなりに有意義なのではないかとは思っています。
長いので、読み飛ばしながら気になるところだけでも目を止めて読んでみてもらえたら嬉しいです。
2月28日:陳情書を作成&提出する
2月上旬のこと、3月に開催される大山崎町議会への陳情書の提出期限が3月頭までであることを知って、できれば提出したいなと思っていました。背景としては、昨年の町長・町議会議員選挙の際、「パートナーシップ制度の導入」が僕の中で重要な争点であったため、Twitter上で町長候補のふたりに制度への姿勢を質問してみました。その結果、両候補ともに導入に前向きな回答だったので、どちらが当選しても制度は導入されるだろうと考えていました(なお、このあたりのことは毎日新聞に取材していただいているので、ぜひ読んでみてください)。
いま思えばこれはとても甘い考えで、選挙が終わり前川光町政が2期目に入って以降も、パートナーシップ制度の導入について検討するような動きはまったく見られませんでした。そこで、次なるアクションとして、議会への陳情書の提出を検討していたのです。
そして2月28日、時間を作ることが出来たので、町のWEBサイトを見ながら陳情書を作成しました。それがこちらです↓
「できた!郵送しよう!」と思って、提出先を役場に電話で確認してみたところ「郵送では受け付けていないので、直接窓口までお持ちください」とのことでした。しかたなく僕はその日の役場が閉まる前に窓口まで行き、無事に陳情書を提出しました。
小さな町なので役場はそう遠くはないのですが、仕事の関係で週末しか動けない人や高齢者など役場まで行くのが困難な状況の人にとっては、とても不親切だと思います。郵送やオンラインでの提出が出来るようにしていただきたいです。
加えて、もっと問題だと思ったのは、町のWEBサイトに記載されているこの箇所です。
請願・陳情書の提出者の個人情報(氏名、住所等)は公表されるというのです。今回僕が行った陳情は主に性的マイノリティの権利を求めるものですが、性的マイノリティに限らず、現状社会で差別や偏見の対象となっている事柄に関して、もし当事者がその経験をもとに陳情を行おうと思った場合、自身の氏名や住所等が公開されるというのは大変危険を伴うことであり、陳情のハードルは極めて高くなります。
その地域でマイノリティの権利が認められていないからこそ陳情を行う必要があるわけで、その場合、その地域でのマイノリティへの偏見や差別は、権利が認められている他の地域よりも厳しいものである可能性が高いです。「陳情」という行為がマイノリティの人々を危険にさらすことになっては本末転倒です。仕組みの改善が必要です。
3月8日:議会事務局より審議される委員会および日程が伝えられる
窓口での陳情書の提出の際に、事務局の方から今後の流れとして「審議される委員会が3月8日に決まる。その委員会で議論・採択が行われて、その結果を持って議会最終日(3月23日)の本会議での審議を経て最終的な採択/不採択が決まる」と教えていただきました。
そして3月8日に事務局の方から電話をいただき、今回の陳情書については「明日3月9日の総務産業常任委員会にて審議されます」とのことでした。3月9日はお店の営業日だったため、「明日か!」とは思いましたが、パートナーと相談して翌日は僕だけお店を早めに抜けて傍聴に行くことにしました。(うちは二人でお店をしているので、一人が抜けるのは相当な負担なんです)
3月9日:委員会の傍聴に行く。衝撃的な展開となる
3月9日の午後、受付を終えて委員会室に入りました。前の議題の議論をしばらく聞いたあと、いよいよ僕の陳情書を審議する時間になりました。正直僕は、全国的に導入が進み、京都府下でも隣の長岡京市を含め導入されているパートナーシップ制度なので、これまでは検討されていなかったとしても住民から陳情書が出されればすぐに導入に向かうだろうと考えていました。が、これはとんでもなく甘い考えだったことがすぐに判明します。
委員会での議論はあまりにもひどいものでした。
自民党系会派の西田光宏議員からは「(パートナーシップ制度は)憲法に抵触する問題だ」との衝撃の発言があり、しかもそれは会派全員で出した結論とのことでした。
憲法に抵触するというならどこがどう抵触するのかその場で示してほしかったですし、既に250以上の自治体で導入済みで人口の6割以上をカバーする制度が「憲法に抵触する」というのは、その認識を疑わざるを得ない発言でした。
さらに、ひとり会派の波多野庇砂議員からは「私の頭ではカバーできない問題」「自分のようなおじいちゃんには判断できない」といった発言が飛び出しました。まさに議論そのものを放棄する発言で、あきれ果ててしまいました。住民からの陳情についてカバーする頭を持っていないと自覚しているなら、すぐに議員を辞めていただきたいです。
このようにあまりにもパートナーシップ制度への理解が足りない議員が多く(そもそも制度自体を知らない議員もいました)、委員長から議論を促されても議論は全く深まらず、結果として「賛成1名(共産):反対2名(自民):留保2名(その他会派)」により「不採択」となりました。
委員会室を出た後、その場にいた複数人と話をしました。名前は言えませんがその全員が委員会室で起こったことのあまりのひどさに愕然としていました。
僕は絶望と怒りに震えつつ、家に帰りました。
3月10日:SNSに怒りの投稿をする
さて、どうしたものか。このままでは最終日の本会議でも不採択となる可能性が高い。そんなことになったらパートナーシップ制度の導入はさらに遅れてしまう。
僕はできる限りの抵抗をしようと決めました。
まず、SNSに怒りの投稿をしました。
とにかくこの状況をみんなに知ってもらって、問題視する人が増えてくれたら事態が変わるかも知れないと思ったからです。今回は特に、普段はあまり使ってないFacebookでの投稿に力を入れました。というのも、Facebookでは町内の知り合いや議員たちとつながっているので、他のSNSよりもインパクトを与えられるだろうと考えたのです。その投稿がこちらです。
委員会での発言を発言者の実名を出して批判しました。
この投稿にはそれなりに反響があり、「最終日は自分も傍聴に行く」という声を多数いただきました。そして、実際、この投稿はそれなりの効果があったようです。後に複数名の議会関係者から「あれはかなりインパクトがあったと思う」と聞いたので、たぶん間違いありません。
SNSでの怒りの投稿に加えて、メディアにも連絡しました。SNSでの拡散には限界があるので、マスメディアにも動いてほしいと考えたからです。知り合いの新聞記者やTVの投稿欄などに委員会での問題発言を含めて連絡し、今のこの状況を取材してほしい旨を伝えました。結果、信頼しているひとりの記者さんが取材を検討してくださるとの連絡をくれました。
今回知った問題点のひとつですが、大山崎町のような小さな地方議会の場合、京都新聞などの地方の新聞社を除き委員会などにメディアの取材が入ることはほとんどないようです。それはすなわち、メディアによる地方議会への監視が極めて弱いということを意味します。
監視の強弱は、議員たちの緊張感に直結します。メディアの人手が足りず、地方議会の実態が報道されずらい問題は、市民生活にじわじわと影響を及ぼしているだろうと思われます。
メディアにはどうかこの問題と向き合ってほしいと思います。また一方で、住民の側もなるべく傍聴に行き、おかしな発言があったときにはSNSでそれを伝えるなど自分たちでできる努力もしていかなければと実感しました。
3月15日:自民党系議員から面談の依頼を受ける
こういった活動がどれほど影響したかは分かりませんが(たぶんかなり影響しています)、3月15日に自民党系会派の議員で、3月9日の委員会で反対票を投じた北村吉史議員(本会議の議長でもある)から電話があり、「陳情の内容について一度詳しく話を聞きたい」とのことでした。僕はそれを了承しました。
3月17日:自民党系議員と面談を行う
3月17日の午後、僕はパートナーとふたりで役場に行き、北村吉史議員と面談を行いました。
面談の内容については、率直に話をするために「SNSなどには書かない」という約束をしたので、ここで詳細には書けませんが、これといって特別な話をしたわけではなく、パートナーシップ制度の意義や僕たちの考える現状の問題点、望んでいることなどを伝えました。そして、それはある程度伝わったと感じました。
3月23日:本会議で全員賛成の「逆転採択」となる
最終的な採択/不採択が決まる3月23日の本会議は、またしてもお店の営業日でした。今回はパートナーも一緒に傍聴することにしたので、お店は閉めて(店の外での無人販売にして)ふたりで議場に行きました。話は逸れますが、大山崎町議会はオンライン配信を行っていないので、直接傍聴に行かないと議論を聞くことができません。平日に行われる議会に住民が傍聴に行くのはとてもハードルが高いです。ぜひ議会のオンライン配信を実現していただきたいです。
さて、この日は10時の議会開始から傍聴していたのですが、議会は揉めに揉めて(町長への辞職勧告決議も出された)、通例だとお昼頃には陳情まで行き付くはずが結局僕の陳情の審議は15時くらいからスタートしました。
冒頭、3月9日の委員会の委員長である朝子直美議員(共産)から、委員会ではこの陳情は不採択となった旨の報告がありました。その報告の中では、「(パートナーシップ制度は)憲法に抵触する問題だ」との発言があったことも紹介されました。
その後、全11議員による議論が行われるのですが、全ての会派が「賛成」の立場で討論を行いました。
委員会では反対の立場で発言した自民党系会派の西田光宏議員は、今回は会派を代表して「賛成」の立場で討論しました。賛成に回ったこと自体はとても嬉しかったのですが、その内容には正直首をかしげるところも多かったです。
たとえば、委員会のときに反対した理由として、「私たちは自民党の党員であり、自民党としては同性婚やパートナーシップ制度に慎重な立場を取っている。党員としてその立場を尊重した」といった旨の発言がありました。つまり、町民から受け取った陳情に対して、自分の考えではなく所属政党の意向の方を尊重したというのです。町民として、町民の想いに真摯に向き合うのではなく、政党の顔色を伺うような議員を信用できるでしょうか。
また、賛成に回った理由としては「行政などとも話をして、同性婚とパートナーシップ制度は分けて考えていいことが分かった」とのことでした。つまり、委員会の時点では同性婚とパートナーシップ制度を混同していたことを認めたわけです。勉強して理解を深められたこと、そして賛成に回ってくださったことは良かったのですが、そもそも議員としてあまりにも理解が不足していますし、日頃からジェンダーの問題に関心が浅いことが分かり、今後もとても心配です。
ちなみに、「私の頭ではカバーできない問題」「自分のようなおじいちゃんには判断できない」と言っていた波多野庇砂議員も賛成に回ったのですが、この日も「自分は専門外」と言っていました。専門外でも採択/不採択を決める権力を持っているのが議員です。勉強し続ける意思がないのであれば、すぐに議員を辞めてください。
結果としては、全員賛成による逆転採択となりました。
本当に良かったです。心からホッとしました。
後から聞いて知ったのですが、委員会から最終日までのこの間、議員間での働きかけや行政職員から議員への制度の説明などが行われたらしく、それらも多くの議員が賛成に回った要因になっているようです。陳情に対してその実現のために、僕の知らないところで色々と動いてくださった方々がいたことに、とても感動しました。
数日後
議決結果の通知書が届きました。
通知書にある通り、次は町長が動く番です。「全員賛成による採択」という議会の判断を受けて、町長にはしっかりと制度を作っていただきたいと思います。
謝辞
今回の一連の活動に対して、様々な形で支援してくださったみなさんにこの場を借りて御礼を申し上げます。
SNSでの投稿に一緒に怒ってくれたみなさん、「いいね!」やシェアをしてくださったみなさん、とても勇気をもらいました。
傍聴に駆けつけてくださったみなさん、すごく心強かったですし、傍聴人の数は議員たちへのプレッシャーになったと思います。最終日の傍聴は過去に例のない人数だったそうですよ!
取材してくださった記者さん、メディアの力は大きいです、本当にありがとうございました。
議会事務局のみなさん、陳情書提出の際の問い合わせから、議員たちへの説明、議会当日の応対まで、ものすごく丁寧にご対応いただき、心から感謝しています。
最後に
今回、僕は人生ではじめて「議会への陳情」を行いました。
途中想像を超えること(=委員会での不採択)があって色々と労力が必要ではありましたが、こうして議会に動いてもらうことができたのはとても嬉しいですし、良い経験でした。
また、今回の活動を見ていた人から「今度は自分で陳情してみようと思った」という声を何人かからもらって、それがものすごく嬉しいです。陳情を出したとして結果がどうなるかは分かりませんが、少なくとも陳情書の提出自体はめちゃくちゃ簡単で、誰にでもできることです。
みなさんもお困りごとや議会への要望などがあれば、ぜひ陳情書を出してみてください!
<修正履歴>
・(2023/04/04)3月17日の議員との面談にはパートナーも同席していたので、表現を一部修正しました。
◎お便りなど募集中◎
お便りフォームにて、あなたのお悩み、質問や感想など何でも受け付けています。それから、各配信のシェアやコメントも大歓迎です!